「京人形み彌け」で
豪華絢爛 雛人形制作。
京人形・十二単
「京人形 み彌け」にて受け継がれる
貴重な技法に習い、
京都選りすぐりの素材に触れながら
制作する「ひな人形」。
「十二単記念撮影館 雪月花苑」では、
本物の平安装束を身にまとった
撮影体験をお楽しみいただけます。
叙勲「瑞宝単光章」を受章した初代・三宅玄祥氏が1969年に創設した『京人形 み彌け』。京都市宇治に店を構え、五十年の歴史を誇ります。『桃の節句(三月三日)』や『端午の節句(五月五日)』は子どもの健やかな成長を願う、喜びに溢れた日本の伝統行事。それを彩るのが、『京人形 み彌け』の『雛人形』や『五月人形』です。
初代・三宅玄祥氏が『み彌け』を創業した当時、雛人形というと表側は絢爛な衣装で彩られていても、後ろ側の目に入りにくい袖の重なりや裾といった部分は簡素な造りのものが主流でした。しかし、初代・三宅玄祥氏が創り出した雛人形は360度どこから見ても美しい雛人形。後部の見えづらいところにまでこだわって、実際に御姫様が座っておられるような、着物の美しい様式を再現しました。創業当時は人形の製造のみを行い問屋に卸していたという同店ですが、画期的な技法は高い評価を受け、それを聞きつけたお客様が直接お買い求めに来られる機会も増えたことから小売りも行うように。人気の下支えには、「絢爛なものでお祝い事を華やかに彩る」という時勢の後押しもあったと言います。
そもそも京人形とは京都の職人が伝統的な手法で作り上げた衣装着人形のことを指し、雛人形をはじめ、五月人形や御所人形、浮世人形や風俗人形、市松人形などといったたくさんの種類があります。中でも雛人形は平安時代以降の公家装束・束帯(そくたい)を身に付けた男雛と、同格の晴れ着十二単(じゅうにひとえ)を身に付けた女雛を模したもので、人々から親しまれてきました。京雛の特徴として挙げられるのは、布の裏に和紙を貼った丁寧な裏地の施しや、時代の流行り廃りに流されない様式美。修理のことまでを考えて剥離できる糊や天然の素材を使用している点も注目のポイントです。
また、京人形の製造は分業化されており、様々な職人の技が合わさって一体の人形が出来上がります。着物と胴体部分を作る胴着付け師や、お雛様のお顔を作る頭師。手足を制作する手足師に、頭部に髪を付ける髪付師。お雛様の持つ扇や冠などを作る小道具師などがいます。
藁を削ったり木を削ったりして胴を制作。そこに艶やかな着物を着つけ、手足や頭、小道具を取り付け、最終的な人形の形を整えるのが『京人形 み彌け』の職人仕事。5工程にも及ぶ職人の叡智と技術を集結し、手作業で人形に命を吹き込んでいきます。
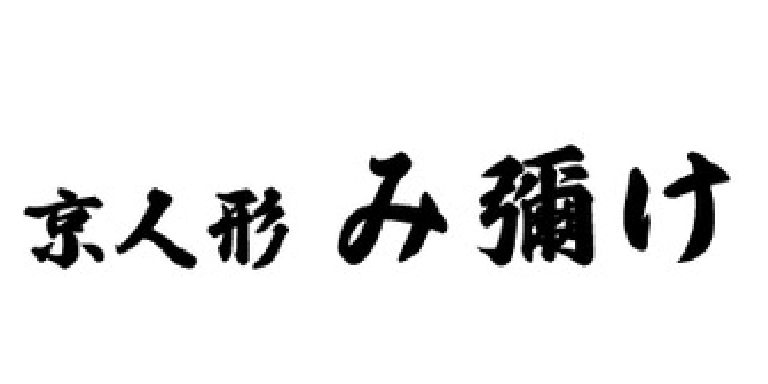

〒611-0042
京都府宇治市小倉町南堀池103-53
TEL 0774-22-5008
www.kyoto-miyake.co.jp

京人形司 ニ代目・三宅玄祥(三宅啓介)
経済産業大臣指定伝統的工芸品 京人形伝統工芸士
初代・三宅玄祥氏は昭和16年、京都市左京区松ヶ崎に生まれました。昭和32年中学校卒業後、15歳にして京人形師『初代・安藤桂甫』のもとへ師事。「物はな、返せ言われたら返さなあかんけど、覚えた仕事は返せ言われても返しようがないやろ。」という言葉に励まされながら、10年に及ぶ修行を経て昭和42年独立。『京人形 み彌け』を創業しました。叙勲「瑞宝単光章」の受章や、京都府伝統産業優秀技術者「京の名工」の表彰を受け、「経済産業大臣指定京人形伝統工芸士」「日本ひな人形協会 節句人形工芸士」として活躍。さまざまな価値ある京人形の数々を手掛けてきました。
二代目・三宅玄祥(三宅啓介)氏は父親の精巧な手作業を間近で見聞きし、幼少の頃より京人形の制作に触れながら成長。大阪の大学を卒業後にインテリア関連会社での勤務を経て、東京都の人形卸販売店にて人形界の修行を積みました。平成6年京都に戻り、京人形の制作に従事。「経済産業大臣指定伝統的工芸品 京人形伝統工芸士」として二代目・三宅玄祥の名を継ぎ、人形界で絶大な評価を受けています。
さらに二代目・三宅玄祥氏は『み彌け‐MIYAKE‐』というブランド名で『甲冑バック(Samurai Armor Bag)』を製造・販売。京人形や京甲冑といった日本の伝統工芸からインスピレーションを得て、その技術を応用・活用されています。世界の方々に手に取ってもらえるような商品の製造・販売をモットーとする甲冑バッグは、五月人形の甲冑をアレンジし、クラシカルな中にモダンなデザインを取り入れたもの。実際に甲冑に使われる鉄などは錆びやすく重いため、本体素材には牛革を使用しています。そしてその上にアルマイトで着色したアルミニウムを縫合。縫製の際には京都の老舗に特注した組紐を使用し、現代の技術と伝統的な技法を絶妙に融合させています。また、実用性も高い甲冑バッグはデザインによって「NOBUNAGA」「MITSUHIDE」「SHINGEN」といった武将の名前や、「CHACHA」といった姫様の名前が名付けられており、作り手の遊び心も感じられる一品。世界各地の展示会に多数出展され、話題を集めています。
「世界にはカジュアルな人形が多い中、京人形は職人の技術が細部にまで凝らされた高価な珍しいものです。体験教室の中でその奥深さを感じてもらったり、日本の伝統工芸に対して親近感を持ってもらえたりするようなきっかけになると嬉しいです」との二代目・三宅玄祥氏の想いが込められた貴重な体験をお楽しみください。
ひな人形コース
「京人形 み彌け」にて受け継がれる貴重な技法に習い、京都選りすぐりの素材に触れながら制作する「ひな人形」。
「十二単記念撮影館 雪月花苑」では、本物の平安装束を身にまとった撮影体験をお楽しみいただけます。

1.生地の選択
まずは衣装の生地を選びます。京都の生地屋さんから特別に仕入れている、人形のサイズに合わせて小さ目に模様が織られた特製の布地を使用。現代の感覚でも愛されるようなシンプルな色味や可愛らしい柄物、歴史ある文様が織られたものなど、十数種類から選んでいただくことが可能です。

2.衿付け
次に、木や綿で作られた御姫様の胴体部分に袴を穿かせた状態のものに、衿を巻き糊付けをしていきます。十二単の中でも衿元の重なりは重要な表現の部分です。丁寧に重ね合わせていく事で、美しい着物姿が出来上がっていきます。

3.衣装の着付け
選んでいただいた生地で誂えた着物を胴体に着せていきます。糊はうなじと衿元にしかつけないので、それ以外は本物の着付け同様、お雛様に着付けていきます。今まで別々に制作されてきた胴体、衣装、手足、お顔、小道具がこの時点で一体となります。

4.完成
最後に目打ちを使って、「かいな折り」と呼ばれるお雛様の腕の振りつけ作業をします。腕の位置をおさめるのは、プロの職人でも難しいとされている作業。慎重に行い、雛人形の完成です。
お土産
京都の伝統的な技法を用い、西陣織の生地で衣装を制作。男雛女雛ともに古典的な有識文様を用い、金沢箔が貼られた金屏風に組み合わせました。
京都 二世三宅玄祥作親王飾り「秀華」
京都の伝統的な技法を用い、西陣織の生地で衣装を制作。男雛女雛ともに古典的な有識文様を用い、金沢箔が貼られた金屏風に組み合わせました。付属品は全て木製。目にも鮮やかなひと品です。
(間口:75cm、奥行き:40㎝、高さ:36cm、人形のサイズ:9番)
古来より人々に幸せをもたらす力があるとされてきた人形。‟人形(ひとがた)“と呼ばれる木や紙でできた人形を海や川に流した行事と、平安時代の‟ひいな遊び”と呼ばれる人形遊びが江戸時代に合体して、“ひな祭り”として祝われるようになったと言われています。雛人形は子どものお守りとして、「愛しいわが子が丈夫に育ってくれるように」との愛情を込めて、親から子へと贈られてきました。雛人形は節分(ニ月三日)から桃の節句(三月三日)まで飾られることが一般的とされていますが、旧暦の節句(四月三日)まで飾る地域もあります。旧暦に合わせて飾るとニヶ月間に渡って華やかな雛飾りを楽しむことができます。また、日本では「三月三日までに雛人形を片付けないとお嫁に行くのが遅れる」などと言われることもありますが、これは日ごろの整理整頓に対する意識を促すため。「ずぼらにならず、きちんとした女性に育つように」との想いが込められたものだそうです。教訓は胸に刻みつつ、技巧の光るお雛様を心行くまで堪能しましょう。

平安装束着装体験
京都伏見深草の『十二単記念撮影館 雪月花苑』では、平安時代当初の平安装束(十二単や束帯)を身にまとうことができます。本物の平安装束を着て、まるで『源氏物語』の中に入り込んだような撮影体験をお楽しみ下さい。

日本で唯一の十二単専門店である「十二単記念撮影館 雪月花苑」にて、本物の装束・十二単を実際に着用し、写真撮影を行います。皇室と同じ技法で仕立てた他にはない十二単を、日本を代表するスペシャリストが着付致します。本物の十二単を着て、金屏風の前でプロカメラマンによる撮影をお楽しみください。
「唐衣(からぎぬ)」「表着(うはぎ)」「打衣(うちぎぬ)」「五衣(いつつぎぬ)」「単衣(ひとえ)」「長袴(ながばかま)」「裳(も)」からなる装束の色や柄を、お好みでお選びいただけます。
また、髪型は伝統的な「大垂髪(おすべらかし)」と呼ばれるものか、現代的なアレンジヘアからお選びください。
十二単記念撮影館 雪月花苑
京都・御所南の地で神社調度品、神官装束の製造・販売をする装束店として昭和4年に創業した『平安装苑株式会社』より、2003年に十二単専門店として独立した『株式会社弥栄』。2017年には現在の伏見の地へ移り、平安装束に特化した日本で唯一の十二単記念撮影施設を開設しました。『雪月花苑』という屋号は、先代より交流のある日本を代表する書道家、杭迫柏樹先生の石碑に由来して命名されたもの。店内には京町屋の雰囲気を残しつつも最新撮影設備機器が設置され、海外からのVIPや国内外の要人にも恥ずかしくない環境で記念撮影を行うことができます。
そもそも十二単とは、平安時代の女性が晴れの場で身に付けていた装束のこと。中国から伝わって来た唐風の衣装が、日本の気候や風土、生活習慣に合わせてゆったりとした形に進化しました。平安時代の女性にとって、十二単の着こなしは自らの知性や教養を表現するもの。「重ね」と呼ばれる装束の配色で季節の移ろいなどを表現していました。「重ね」の名称には王朝人に愛された花などにちなんだものが多く、その季節にふさわしいものがつけられています。また、平安時代の衣装は着物とは違い、張りのあるしっかりとした布地が用いられていました。現在も一寸三針という粗い目の装束仕立てで、大きくゆったりと作られています。現在でも十二単をはじめとする平安装束は日本の皇族の方々が儀式の際に身に付けられ、その伝統は時を超えて受け継がれています。
こうした本格的な十二単の着装体験・記念撮影を手がけている同社。撮影は一日あたり午前・午後のニ組限定で、ゆったりとした雰囲気の中、まるで平安『源氏物語』の世界へとタイムスリップしたかのような非日常感を楽しむことができます。撮影に利用する座敷は15畳の広さで天井も高く、立ち姿も撮影可能。座敷内の畳は高麗縁の小紋で、平安時代の貴族が用いていたものを使用しています。さらに平安時代の貴族がお目出たいお祝いの際に用いた美麗几帳を使用して、雅やかな撮影をお楽しみください。金屏風の前では皇室の婚礼と同様の撮影も行う事が出来ます。
千年以上続く伝統装束を身にまとい、こころゆくまで、装束の素晴らしさを体感することができます。
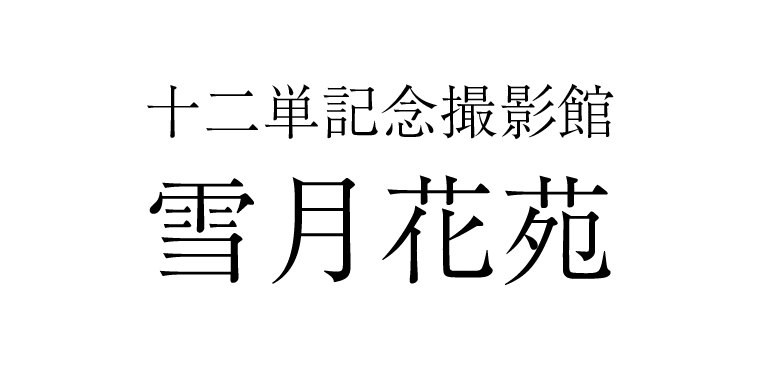

〒612-0029
京都市伏見区深草匹涌町2丁目123-3
TEL 075-642-1028
junihitoe.jp

宮廷装束研究家 福呂一栄 株式会社弥栄代表
平成の御大典の際、皇后さまより「今後、ますます多くの皆様に十二単を伝えていってください」とのお言葉を拝受したという十二単の第一人者・福呂悦子氏から十二単制作の伝統と技術を継承した福呂一栄氏。四十年親子二代にわたり、衣紋道・山科流先代家元や日本を代表する有識故実の先生方にもご指導頂ききながら、知識の習得や継承に励んで来られました。教科書などの書籍やNHKなどの放送番組、東京ビッグサイトなどでの十二単展示会やファッションショーの開催、各種教育機関などでの講演・展示の実施など、十二単や束帯の啓蒙、日本文化の継承活動を数多く実施されています。
80余年装束店を営む『平安荘苑株式会社』のもと、JR東海主催の十二単着付け体験と講演がきっかけとなり、1998年に『平安装束体験所』を開設。2013年に「株式会社弥栄(いやさか)」として独立しました。弥栄には「生きとし生けるもの全てが栄えますように」という意味が込められているそうです。そうした意味合いを踏まえ、弥栄の衣装には「お召しいただく皆様が栄えますように」との想いが込められ、平安人が繁栄や長命を願い着用した色目や文様が用いられています。また、同社では伝統に裏打ちされた宮中における制作技術を踏まえつつ、独自にアレンジを加えた十二単の制作も手掛けています。
ひと針ひと針、福呂一栄氏が祈りを込めて縫い上げた十二単は現代の若い方々にも、1200年の間脈々と受け継がれてきた十二単をはじめとする平安人の衣装に込められた想いや気持ちを感じながら、それぞれの人生を幸せに過ごしてほしいという想いを込めて作られました。



